運動のあとや暑い場所で汗をかくことは代謝によるものであり、ごく自然なことです。
ただ、僕は通勤時にたった10分歩くだけで汗が吹き出します。
リュックを背負っていますが、自席に着く時には背中がびっしょりになります。リュック背負ってる人いっぱいいるけど何で汗かいてないの?って不思議に思います。
しかも、僕は背中とお尻が特に汗をかきやすいようで自転車に乗ったり、ベンチに座ってるだけでズボンのお尻部分が濡れてしまいます。
そして、最悪なのが臭い。
これどうにかならないかなって思ったのがきっかけで、汗について調べてみたので解説と汗体験談を紹介をしていきます。
『汗のしくみを知りたい方』『汗対策を知りたい方』にぜひ読んでほしいです。
汗をかくときはいつ?
汗をかくときのシチュエーションを整理してみます。僕は以下のときに汗をかきやすいと感じています。
体を動かしたとき
通勤時に駅から会社まで10分程歩くだけで汗びっしょり、自転車を15分程乗るだけでお尻がびっしょり、ベンチに座っているとお尻がびっしょり。
夏はちょっと動いただけで汗が吹き出します。冬はあえて薄着にしているので、夏ほど汗はないですがじんわり汗をかきます。
これは体温の上昇による汗で、体温調整のために汗を出し気化熱で体を冷やす目的のものです。

お尻の汗はズボンまで濡れてしまうことがあり、漏らしたように見えるのでほんとに嫌です。
緊張したとき・ドキドキしたとき
子どもの行事などで『ちゃんとできるかな~』ってドキドキしている時に手のひらに汗をかきやすいと思います。
仕事で大人数の前で説明したりして緊張するときがありますが、そういうときは汗が出ない。
心配症ということなんですかね。
これは、緊張やストレスなど精神的な刺激で、手のひらや脇など局所的に汗をかきやすいです。

見守るってドキドキしますよね。
辛いものを食べたとき
辛いものを食べたときも汗が吹き出します。
・・・というより、例えば唐辛子系の匂いを嗅いだだけでじんわり汗が。なので、辛いものが嫌いではないですが、汗が気になるので辛いものは避けることが多いです。
辛いものを食べたときは、頭から汗が吹き出します。これは、味覚による汗です。

匂いだけで汗かくって感度高すぎって思ってしまします
汗の出どころ
汗は汗腺(かんせん)という器官からでてきます。汗腺には『エクリン腺』と『アポクリン腺』の2種類あります。
それぞれの汗腺を解説します。
・全身に分布していてる腺
・体温調整のために汗を出す
・汗腺のサイズが小さいので小汗腺といわれる
・わきの下などに分布している腺
・精神的刺激などにより汗を出す
・汗腺のサイズが大きいので大汗腺といわれる

体を動かしたときの汗は『エクリン腺』、ドキドキしたときや辛いものを食べたときの汗は『アポクリン腺』ですね。
汗のない生活=汗腺の衰え
僕は通勤時に歩いたりしたときは汗をかきやすいですが、会社でデスクワークをしているときは全く汗をかきません。むしろ、空調が効きすぎて手が冷たいときもあります。
汗で嫌なのは夏の通勤時です。振り返ってみると、汗をかくのって夏の通勤時くらいであとはほぼ汗をかかない生活です。
汗をかかないと、汗腺が衰えて(または機能しづらくなって)しまいます。
汗腺が衰えると、汗が臭ったり、べたついたりします。
汗が臭う
汗が臭うシステムは以下のようになります。
汗腺が衰えてる状態で汗をかく
↓
汗が皮膚にある皮脂・アカと混じり合う
↓
皮膚にいる常在菌が汗と混じり合った皮脂・アカを食べる(分解する)
↓
汗が臭う
汗自体に臭いはありませんが、常在菌が皮脂やアカを食べて分解すると臭いが発生します。
常在菌がいなければ・・・と思いますが、常在菌は皮膚に病気などの細菌を抑えるので、いないと困るヤツなんです。
汗がべたつく
汗腺にはミネラル等を再吸収する『ろ過機能』があり、ちゃんと働けば水分のみの汗になりますが、うく働かないとミネラルを含んだ汗となります。
ミネラルを含んだ汗は、『べたつく・蒸発しにくい・臭いやすい』の3拍子が揃った汗になります。
まさに、不快。それだけです。

学生時代は臭わなかったのに・・・って方は、汗をかく頻度が減って汗腺が衰えたことが原因の一つとしてありそうです
衰えた汗腺を正常にする方法
衰えた汗腺はどうすれば正常に戻るのか。それは、汗腺を鍛える!
鍛える方法はただ一つ、『汗をかく』
汗をかけばどんどん鍛えられて、『ろ過機能』が高まります。それにより、『サラサラ・すぐ乾く・臭いにくい』汗になります。
汗をかくのにおすすめなのが、ウォーキング(有酸素運動)や入浴です。

汗をかくものは汗を制す
ウォーキングで汗をかく
ウォーキングは、いつもより早歩きで行います。汗のかき方は個人差があるのでこれと決めれませんが、だいたい20分くらいで汗をかきます。(季節により変動あり)
全身からじんわり汗がでる程度を継続すると、汗腺が鍛えられてきます。
ウォーキングは運動不足解消にもなるのでいいことがいっぱいです。

有酸素運動は全身の血流がよくなるので、汗をかくのに最適です。
ランニングやジョギングもいいですね!
入浴で汗をかく
湯舟に浸かって、汗を流します。
半身浴で時間をかけるもよし、入浴剤を入れてリラックスするもよし、何も考えずにのんびりするもよし。温浴効果で全身に血液が循環し汗をかきやすくなります。
ただ、湯舟に浸かっているので、汗かいた~っていう達成感的なものは感じないかもしれません。
入浴はとてもリラックスでき、体が芯から温まり自律神経を整える効果もあります。

長時間入りすぎて、のぼせない様にご注意ください
汗対策を紹介
汗腺のろ過機能を正常に戻せば問題解決になりますが、汗をかく継続的な取り組みが必要だし、その間ずっと不快な思いはしたくいと思い、汗対策というか汗とのうまい付き合い方を試してきました。
その中で効果のあったものを紹介します。

汗を止めれないなら、どうしたら目立たなく出来るか試しました!
トートバックを使う
片手持ちのビジネスバックを使っていましたが、肩こりのためリュックを使っていました。
大容量入るし、両手あくし、両肩に負荷がかかるから肩が凝りにくいし、気に入っていましたが、夏になると背中がびっしょり。背中だけシャツの色が変わってる。。。
リュックは便利ですが、背中が密着してるため通気性が悪くなり汗をかきやすいことに気付きました。
そこで、通気性がよくて、容量もそこそこあって、出し入れもしやすいものを探してみたらトートバックを発見しました。
肩こりの心配がありましたが、左右入れ替えて持ち、肩がこらないように注意していくしかないかなと妥協しました。
相変わらず汗はかきますが、背中の通気性がよくなったのでだいぶ良くなりました。
黒系のズボン
濡れても分かりにくい色の服を選ぶようにしています。
黒とか濃い色の物は汗をかいても分かりにくいのでおすすめです。グレーとかオレンジとか赤は濡れると色の変化が大きいので避けた方がいいと思います。
インナー(肌着)を着る
夏はTシャツ一枚で過ごしていましたが、汗をかくとシャツが濡れてしまい困っていました。
そんなとき、子どもが肌着の上にTシャツを着ているのを見て、真似てみたらビンゴ。肌着が汗を吸収してくれるので、シャツまで濡れなくなりました。
吸水性・速乾性の高い肌着が売られているのでこれはほんと神です。肌着は汗を吸収しているので臭いますが、その上に着ているシャツで臭いが漏れにくくなっているので、電車で臭いが気になるとことがすくななくなりました。
吸水性・速乾性に優れているのが、ジオラインを使った【モンベルのジオラインクールメッシュTシャツ】です。
【モンベル/ジオラインクールメッシュTシャツ】をチェックする。
Yシャツの下に着ても透けないので、使い勝手が良いです。
汗対策のSNSでの口コミを紹介
汗対策についてSNSの投稿を紹介します。
手汗対策ってなにしてる?
— HNg_もち麦ボーイ. (@110mrgv) January 15, 2023
その他はどんなのかリプくれると嬉しいです!
ほんとこれ。機械の体欲しいです!
【汗っかきの女性の方の制汗対策4ステップ】
— ヒミツの♡女子力UP術.:*☆ (@jyosi_study) January 14, 2023
①外出時、着替える前から全身にベビーパウダーを着けておくとお出かけ前の汗をかなり抑えらる。
②汗をかいてもこまめに水分補給する。
③タオルを多めに持っておく。
④制汗剤をすぐ取り出せるようにする。
制汗対策で多いのが制汗剤です。夏は必需品ですね。
夏のニオイ対策!
— オアシス (@oasisda88) January 12, 2023
脇汗対策の長持ち方法!
朝、わきの中心にロールオンかクリームタイプのデオドラント商品をつけたら、スプレータイプもかけてダブル対策
これで効果が長持ちします!
制汗剤はスプレーや直塗りタイプがありますが、ダブル対策で効果長持ちするとの投稿もありました。
日照り対策、汗対策として帽子やタオル、吸水性のいいインナーなどは基本中の基本
— スポーツ医学+脳科学bot (@smc_bot) January 16, 2023
この方は自分にあった汗対策を実施していますね!

みなさん、自分にあった汗対策をしてるのがわかりました!
まとめ
不快な汗についての解説と汗対策を紹介してきました。
まとめると、
- 汗腺のろ過機能が低下により不快な汗になる
- 汗をかくと汗腺が鍛えられ、ろ過機能が強化される
- ウォーキングや入浴で汗をかく習慣をつける
- 汗対策(自分にとって不快にならない、汗との付き合い方を考える)
汗は生体機能上なくすことはできないものなので、上手に付き合っていきましょう。

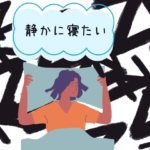



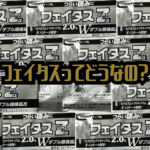

コメント